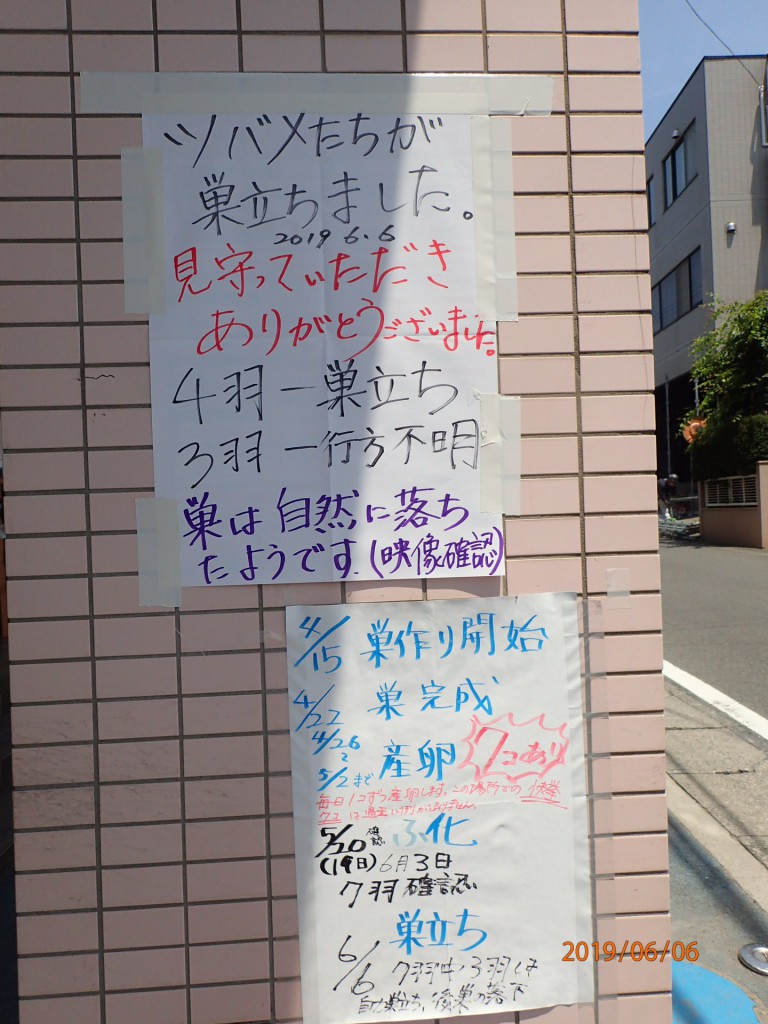< こども環境管理士 受験申込 >
子どもたちの未来に何が必要か。
世界ナンバーワンの大学と言われるハーバード大学の入試で重視されることは、
①パーソナリティー(人格)の多様性と人と違う個性
②困難を乗り越える力や物事への情熱のあり様
③今できることではなく、これからどんなことをやってくれそうかの潜在能力
だそうです。動物である人が持つ秘めた能力をどれだけ発揮できるかを問われるわけです。
幼児期から保護者が思う、学ばせたい事柄に専念させるのではなく、広く、楽しく興味をつなげ、自分の頭で展開する思考を作るには、
こども環境管理士は自然を通して子どもたちの意欲や興味を後押しする、
幼稚園・保育園・小学校の先生方に是非進めたい学びです。(資格です)
●「こども環境管理士資格試験」は、環境教育等促進法に基づき
環境大臣・文部科学大臣により環境人材認定事業に登録されています。





 そして池ではクモに捕まったアメンボウ。
そして池ではクモに捕まったアメンボウ。 そして小さな虫を捕まえた、ヒメアメンボウ。食う、喰われる世界では日々死闘が繰り返されています。
そして小さな虫を捕まえた、ヒメアメンボウ。食う、喰われる世界では日々死闘が繰り返されています。 そして本日、トカゲのとかちゃんが3つの卵を産卵しているのを確認しました。写真がボケていてすみません。幼稚園で飼育したトカゲで産卵は初めてです。
そして本日、トカゲのとかちゃんが3つの卵を産卵しているのを確認しました。写真がボケていてすみません。幼稚園で飼育したトカゲで産卵は初めてです。